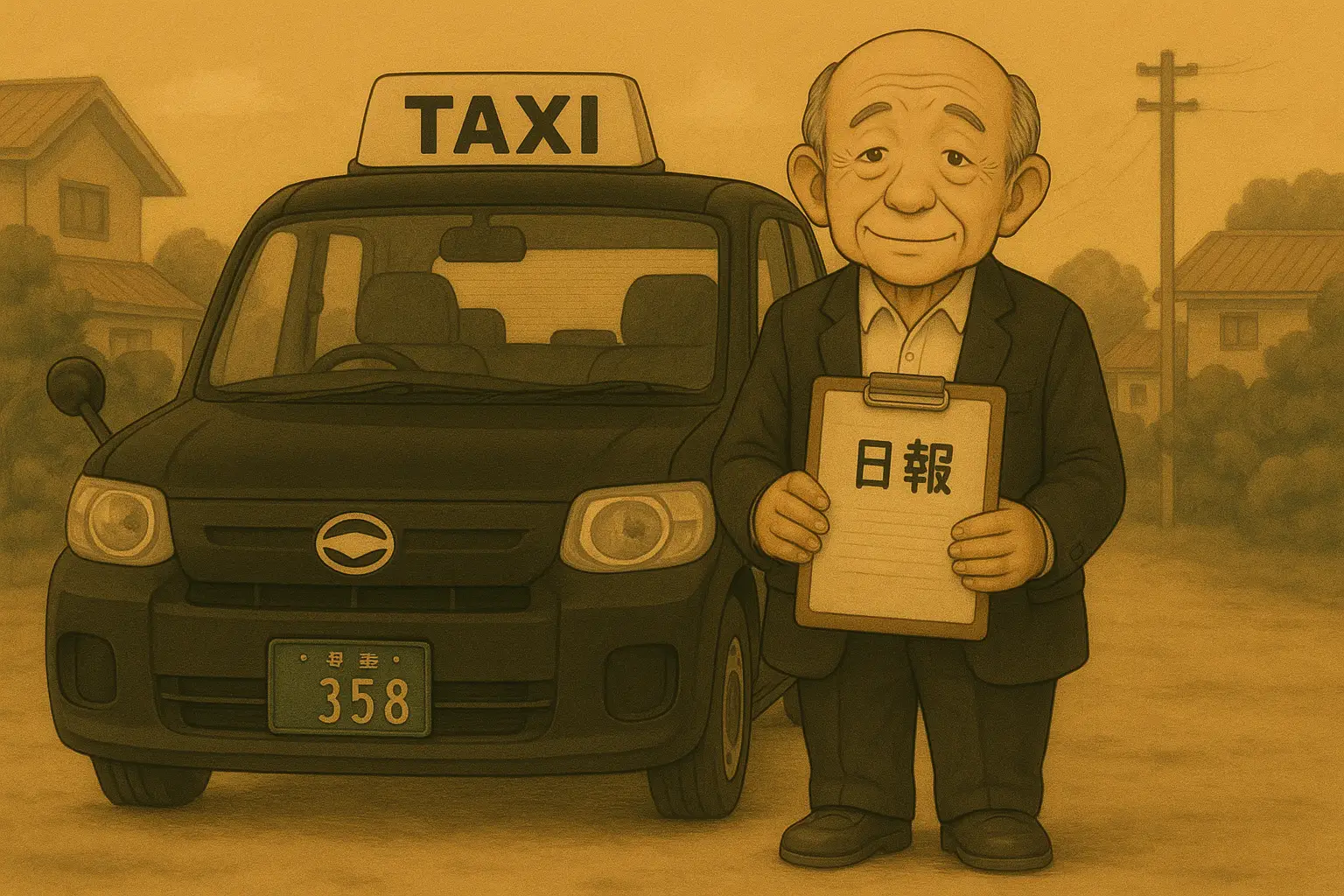近年、タクシードライバーとして新たなキャリアを選ぶミドルシニア(中高年)の方々が増えています。
自動車教習所の二種免許取得のための学科やタクシードライバーとしての初任者研修ではミドルシニアの受講生を本当によく見かけました。
特に未経験からの挑戦には不安がつきものですが、実際に多くのミドルシニアがタクシードライバーとして活躍しています。
苦労もありますが、筆者は楽しくやっています。
この記事では、「未経験からタクシードライバーになる方法」や、「ミドルシニアが直面する課題とその解決策」を分かりやすく解説します。
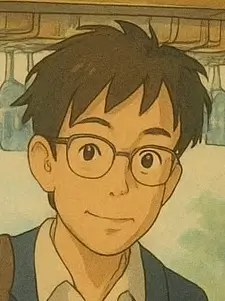
観光が盛んな地方在住のアラフォーの現役タクシードライバー
特徴:不器用、人懐っこい、人との距離感バグってる
家族:妻と男の子1人
過去のキャリア
– 地方公務員(企画・立案)
– プログラマ(ミドルウェア)
– 福祉業界(営業職)。
– 多様な経験を現在の接客に活かす。
ミドルシニアがタクシードライバーとして働くための課題とその解決策
タクシードライバーとして働くには、特に未経験者やミドルシニアにとっていくつかの課題が存在します。
以下に、それぞれの課題とその解決策を詳述します。
身体機能・健康面の課題

ミドルシニアは持病を抱えるお年頃なので、健康状態が業務に影響します。
お客様を安全に送り届けるという業務のため、健康管理について会社は敏感です。
体力の低下
長時間の運転や荷物の積み下ろしなど、思いのほか体力を使います。
加齢により体力が低下しやすくなるため、長時間運転後の疲れが取れにくくなることが課題です。
筆者も若い時はロングドライブも楽しくて大して疲れを感じませんでしたが、歳を重ねると運転は楽しくても次の日に目も身体も疲労がなかなか残ります。
解決策
働き方に配慮したタクシー会社を選ぶ
筆者の会社では平均して7時間の勤務が続きます。
体力に応じた勤務時間の調整が可能な会社を選ぶことで、無理なく長期間働けます。
事前に健康管理を相談
就職活動の時は健康診断の機会や体調の不調に合わせた勤務調整が可能か確認しましょう。
健康状態の不安
認知機能や視力、聴力の低下が懸念され、これが安全運転に影響を与える可能性があります。
解決策
弊社では昼日勤は年に1回の健康診断、夜日勤は年に2回の健康診断があります。
- 定期的な健康診断を受け、体調不良時には運行管理者に相談することで無理なく働ける環境を作りましょう。
解決策
- 早めにタクシー協会で適性検査を受け、運転や認知機能のチェックを行い、必要な場合はカウンセラーや運行管理者からサポートを受けるようにしましょう。
制度的な課題

雇用条件の厳しさ
タクシー事業者によっては、年齢制限や就労時間の原則を定めている事があります。
しかし、パートタイマーも募集している事業所もあるため、求人内容について問い合わせてみましょう。
筆者の地域では営業所によっては昼夜ともに遊休車両があるため、まだまだ人材が不足している様子が見られます。
解決策
短時間勤務や柔軟な勤務日数を導入している会社を選び、無理なく働ける環境を整えることが重要です。
筆者の会社は勤務時間については相当な短時間勤務が続くとかでもない限り、注意されることはありません。
筆者の乗務は平均7時間程度です。
車両の給油・清掃、前後の事務作業などを含めて8時間弱です。
同僚にはもっと短時間の方もいます。
このように、無理なく長く働ける環境を確保するために、短時間勤務以外に体力に応じた勤務日数(シフト)を設定してもらえるか会社説明会や面接時などに事前に確認しましょう。
「中高年も歓迎」といった見出しの求人がハローワークで見つかる事があります。
弊社もハローワークに求人を出し、まだまだ人材確保に努めています。
心理的な課題

新しい環境への適応
タクシードライバーとしての業務に必要な知識や技術(地図アプリやメーターの操作など)を覚えることが、特に未経験者にとっては心理的な負担となります。
運転以外に求められる機器操作が世間が思うより多岐に渡ります。
ケースに応じてメーターを利用しての運賃請求か、定額契約のためメーターが不要など様々なケースがあります。
筆者はどんくさいので覚えるのにめちゃくちゃ苦労しました。
マニュアルが用意されている事もありますが、書いて覚えるという意味でもメモは有効です。
解決策
研修期間中にベテランドライバーとの同乗研修を受けることで、新しい技術や知識を効率よく学べます。
研修はタクシー会社によって異なります。
期間や内容は事前に確認しましょう。
筆者の研修は2週間でしたが、タクシー事業者によっては1週間なこともあります。
関連記事 タクシードライバーデビュー前の研修に関する記事はこちら
安全運転へのプレッシャー
タクシー運転手は乗客を安全に送り届けるという重い責任があります。
特に中高年層にとっては、このプレッシャーがストレスになることがあります。
解決策
研修期間中における適性検査により、運行管理者たちは個々の特性を把握し、個別サポートの適正化を図っています。
弊社では、出社・退社時のアルコール検査、体温測定、体調に不安がないかなど、対面して様子をみて、運行管理者が気を配ってくれます。
社会的な偏見
「中高年ドライバーの運転は危ない」「運転できれば誰でもできる仕事」という社会的な偏見がいくらか存在します。
この偏見が、ミドルシニアのタクシードライバーとして働く意欲を低下させる可能性があります。
解決策
タクシー事業者は求人の際に、タクシードライバーは地域に貢献する仕事である事、人々の生活はドライバーであるミドルシニアの活躍に支えられている事を発信して安心して働ける環境の提供に努めています。
経済的な課題
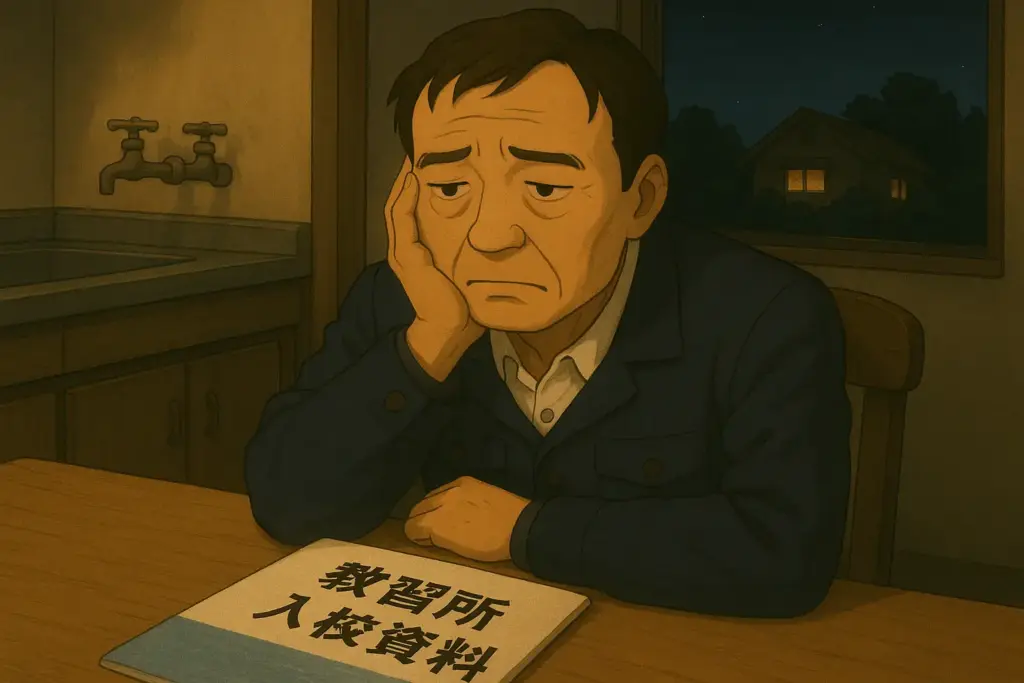
二種免許取得費用の負担
二種免許の取得には自動車教習所での講習を受ける必要がありますが、20~30万円程度の費用がかかります。
ミドルシニアの方々は子育てで家計に余裕がない場合も多いため、この負担が大きな障害となることがあります。
筆者はタクシー会社の養成制度で二種免許を取得しました。
解決策
地域によっては、タクシー会社が二種免許取得支援を行っている場合があります。
求人情報や会社説明会で詳細を確認し、養成制度を利用しましょう。
収入の不安定さ
タクシードライバーの収入は歩合制であるため、安定しないことがあります。特に子育て世帯のミドルシニアにとって、この収入の不安定さは大きな不安要素です。
解決策
安定した収入を得るためには、事業者およびドライバーが安定した収入を得られるための営業努力が必要です。
タクシー事業者は空港や病院、観光施設での待機場の確保に努め、事業者やドライバーの収入基盤の強化を図っています。
さらに、多様な決済方法に対応し(アプリ・電子決済の導入)、効率の良いマッチング、選ばれるタクシーになるために努力しています。
初期投資の負担
タクシードライバーとして働くためには、制服や運転に適した靴などの購入が必要です。
解決策
制服支給があるタクシー会社を選ぶことで、初期投資を軽減することができます。
制服を一式支給する会社もありますが、シャツのみという会社もあります。
この辺りは事前に会社に確認しましょう。
社会的なサポート
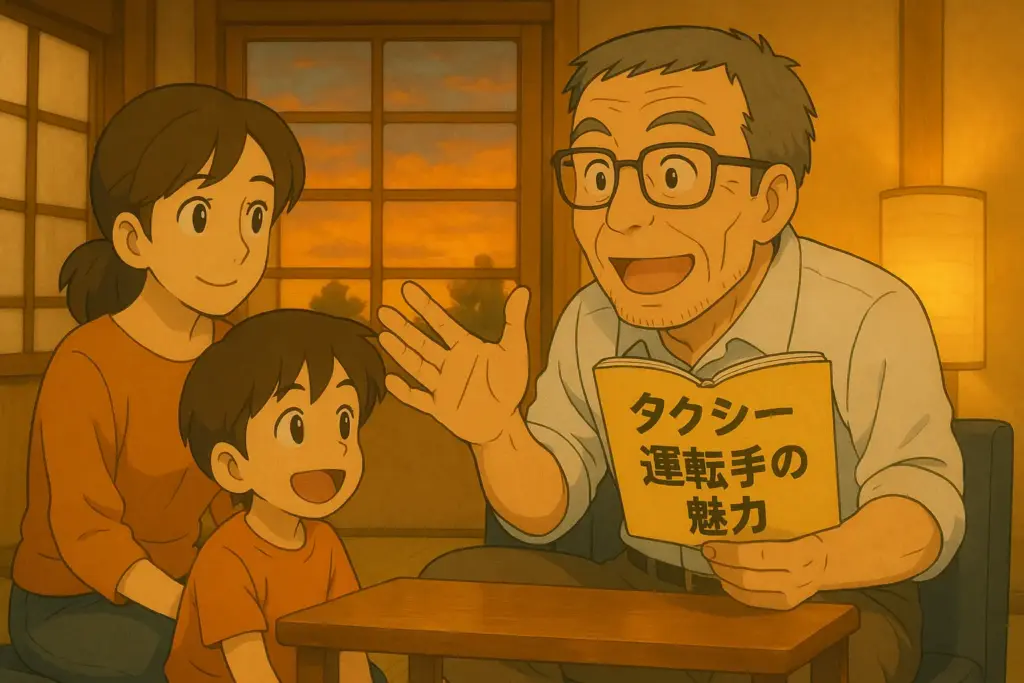
家族や周囲の理解
ミドルシニアが新しいキャリアに挑戦する際、家族や周囲の理解とサポートが重要です。
筆者の場合、妻は理解を示してくれましたが両親は反対しました。
口だすなと言い返しました笑
解決策
家族や周囲の不安を取り除くため、まず本人がタクシードライバーの魅力を理解し、そして周囲に伝えてください。
地域におけるタクシーの役割を説明し、やりがいのある仕事であることを家族に理解してもらいましょう。
成功するために必要なこと

タクシードライバーとして成功するためには、地域のタクシー会社の実情をしっかり把握し、自分に合った勤務条件を整えることが大切です。
解決策
求人情報を通じて他のミドルシニアがどのように働いているかを調べ、適切な働き方を選びましょう。
当たり前ですが、タクシー会社で環境は異なります。
気になる会社のタクシーに乗車し、勇気を出して現役ドライバーに色々質問して業界や所属会社の環境について探るのもありです。
まとめ
未経験からタクシードライバーとしてのキャリアを築くには、いくつかの課題が立ちはだかりますが、適切な解決策を講じることで、ミドルシニアでも十分に成功を収めることができます。
経験豊富な方々がタクシー業界に活躍の場を広げており、その豊富な知識と経験が乗客や社会に大きな貢献をしています。
自信を持ってタクシードライバーとしての新しい一歩を踏み出してください!
ミドルシニアの豊富な経験や知識を活かし、お客様をはじめ、あなたも関係者も、皆がハッピーになれるよう頑張りましょう!
関連記事 未経験からタクシードライバーへ転職|地方・昼日勤で実現する「家庭と仕事を両立できる」働き方【現役ドライバー体験談】